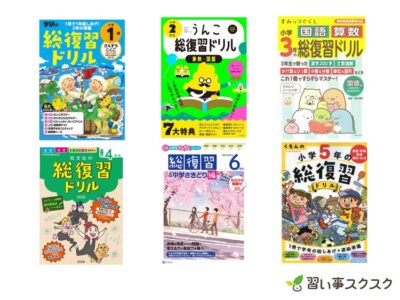「声を出す」ことはテクニックの1つ!少年サッカーで効果を発揮する声出しトレーニング
子どものサッカーの試合を見ていて、「なんでもっと声を出さないんだろう」とモヤモヤしてしまう親御さんも多いのではないでしょうか。「声を出すことは、ドリブルやシュートと同じくらい大事な技術の1つ」そう語るのは北海道札幌市の『真栄サッカースポーツ少年団』の塩崎コーチ。
今回SUKU×SUKU(スクスク)では塩崎コーチのYouTubeから「家庭でできる声出しの練習3選」「サッカーにおける良い声3つ」について紹介します!
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
- 声を出すこと=サッカーテクニックの一つ
- サッカーに効果的!家庭でできる声出しの練習3選
- ①家庭内での基本的な挨拶
- ②子どもに尋ねる・質問する
- ③会話で意見を聞く
- 少年サッカーで効果を発揮する「3つの声」
- ①指示する声
- ②仲間の気持ちを助ける
- ③自分・チームの気持ちをUPさせる
- まとめ
- 今回ご協力いただいた教室
- コチラの記事も読まれています
声を出すこと=サッカーテクニックの一つ
今回SUKU×SUKU(スクスク)がピックアップしたYouTubeはこちら。
真栄サッカースポーツ少年団で指導歴10年以上を経験する塩崎コーチ曰く、サッカーにおいて『声を出すこと』は大事な技術の1つだそう。
「子ども達それぞれの性格や特徴もあるので一概に声出しを強調するわけではないのですが、試合中に大きな声を出すことができれば、よいことのほうが多い」とYouTubeのなかで話されています。
サッカーに効果的!家庭でできる声出しの練習3選
①家庭内での基本的な挨拶
まず1つめは『家庭内での基本的な挨拶』。

塩崎コーチ
おはよう、おやすみなさい、ありがとうという言葉は何気ない基本的な挨拶ですが、子ども達は意外と家庭や学校で忘れていたり、できていないということがよくあります。
じつはチームの子どもでも、目を見て話しているのに知らんぷりしてしまうこともあります。そうしたときには、必ず呼び止めて挨拶をきちんとするよう口うるさく言っています。
じつはこうした基本的な言葉を、当たり前に口に出すことを日々習慣づけることは、声を出すためのトレーニングになるのだそう。
どれもごく基本的な挨拶なので、家庭でも改めて意識し、習慣づけられるよう心掛けていきたいですね。
YouTube 1:39~ 家庭内での挨拶
②子どもに尋ねる・質問する
2つめは『子どもに尋ねる・質問する』こと。
具体的な例でいうと、よく家庭内で口にしがちな「宿題をやりなさい」という言葉。これを「宿題やらなくて大丈夫?宿題やらないと明日どうなるかな?」という言葉にチェンジするとよいそうです。
2つの言葉はどちらも「宿題をやりなさい」と子どもに呼びかけている言葉ですが、塩崎コーチは後者の言葉がけを実践するべき理由について、次のように話されています。

塩崎コーチ
この理由は、文末を疑問形にすることで子どもが一度頭のなかで考えるようになり、会話が生まれるからです。
ワンパターンの返答しかできない言葉がけをするのではなく、子どもに考えさせることを意識しながら話すようにすることが大切なんです。
いつもの言葉を疑問形にチェンジする。
この方法もサッカーの試合で子どもが「考えて声出しをする」ことにつながるのだそう。こちらも家庭で気軽に実践できそうですね!
YouTube 2:32~ 子どもに尋ねる
③会話で意見を聞く
3つめは『会話で意見を聞く』こと。
たとえば「サッカー楽しかった?」「お昼のご飯おいしかった?」と子どもに聞くと、「うん」とワンパターンの返事が返ってきがち……。
塩崎コーチ曰く、この質問の仕方を具体的な返事が返ってくるようにチェンジすることが大切なのだそう。

塩崎コーチ
「今日の相手はどうだった?」
「どんなところが強かった?」
と聞くと、子どもは考えながら「強かった」「あのね~相手の何番がね~」と自分の意見や思ったことを言葉にして発信するようになってきます。
じつは指導者も普段、何気ない雑談も大事にしています。たとえば「給食なんだった?」「試合終わったら何する?」など、こうした雑談を通して子どもの性格や学校の様子が分かってきます。ときに意外な一面を見れたりすることもあり、それがサッカーのポジション配置や適材適所を考えることに役立つんです。
何気ない子どもとの会話がポジション配置にもつながっているなんて、とてもびっくりですよね。
実際に塩崎コーチがいつも遊んでばかりいそうな子どもに「サンタさん何頼んだ?」と質問したときに、「本をお願いした」と意外な返事が返ってきたということがあり、そうした意外な一面を知ることも、サッカーの配置を考えるときに役立ったのだといいます。
意見を聞くことを家庭でも取り入れると、思ったことを言葉にする力が育まれ、子どもとの関係向上にもつながり、まさに一石二鳥ですね!
YouTube 3:24~ 会話で意見を聞く
少年サッカーで効果を発揮する「3つの声」
つづいてサッカーではどんな声を出すとよいか紹介している塩崎コーチのYouTubeを紹介します。
塩崎コーチは、自分自身やチームのためになる『良い声』には3つの種類があると話されています。
①指示する声
まず1つめは『指示する声』。
たとえば「〇番をマーク!」「後ろに相手いるよ!」「左空いてるよ!」といった、直接試合の勝ちに結びつく声です。

塩崎コーチ
指示する声はレベルが高い声出しです。
指示する声が出せる選手は、サッカーをたくさん知っていて、試合中に自分だけではなく周りが見えていることが前提となってきます。
逆にいえば、こうした声出しができる選手は、サッカーがまだよく分かっていない周りの子達に詳しく教えてあげることができます。仲間がうまくなることはチームがうまくなることにも繋がるので、サッカーに詳しい選手は指示する声をたくさん出していってほしいです。
レベルが高い声出しではありますが、お子さんがサッカーについてもっと詳しくなれるように、家庭でも試合の動画を一緒に見るなどして自然と試合中に指示する声が出せるよう導いてあげたいですね。
YouTube 2:22~ 指示する声
また、良い声とは反対に言ってはいけない言葉も紹介されています。

塩崎コーチ
「おい!決めろよ」「しっかりやれよ」「なにやってんだよ」といった仲間が落ち込む言葉は絶対にだめです。
言われる側は一番分かっていて、仲間から言われることでさらに追い打ちをかけられてしまい、それ以上よいプレーができなくなってしまいます。このため、チームの指導者はシュートが入らなかったときには、「次があるよ」などポジティブな言葉をかけるようにしています。
さらに「ダメな言葉ばかり使い続けている選手は、絶対にサッカーがうまくなれない」とも。
たかが言葉、されど言葉。自分も相手も心から前向きになれる言葉を日頃から子どもが発することができるよう、家庭でもサポートしていってあげたいですね。
YouTube 1:00~ ダメな言葉とは
②仲間の気持ちを助ける
2つめの良い声は、「大丈夫!次あるよ!」「切り替えていこう!」「ナイスプレー!」といった『仲間の気持ちを助ける声』です。

塩崎コーチ
こうした言葉をかけられると、ミスしたほうも落ち込まずに前向きになれます。これはサッカーがよく分かっていなくてもみんなが発することのできる声出しです。
何を喋ったらよいのか分からないという選手は、ぜひこうした声出しを積極的にしていってほしいですね。
YouTube 3:28~ 仲間の気持ちを助ける
③自分・チームの気持ちをUPさせる
3つめは「声出していこうぜ!」「絶対勝とうぜ!」「先に触ろう!」といった『自分・チームの気持ちをUPさせる声』です。
こうした声出しは、大人になるにつれ発することが難しくなってくる言葉ですが、小学生であればまだ元気いっぱいに発しやすい声でしょうね。
塩崎コーチも「恥ずかしがらずに、どんどん大声を出していってほしい。そうすることで緊張がほぐれて自分もチームもよいプレーができるようになる」と仰っています。

塩崎コーチ
こうした盛り上げ隊のような声出しができる選手が何人かいると強いチームになることができます。
4~5人声を出せる選手がいるチームはギリギリの戦いで勝てたりすることが多く、指導者もよいチーム作りがしやすいですね。
また、声を出すことで
・緊張している選手のサポートができる
・チーム全員で一致団結できる
・相手チームが声出しに圧倒され、その勢いで先手が取れる
など嬉しい効果がたくさんうまれてくるのだそう!
とくに小学生のうちは恥ずかしがらず、うるさいくらいにどんどん声を出して試合を盛り上げていくのがよいとのこと。

塩崎コーチ
すべての声出しをいきなりやるのは難しいので、得意なことを1つでもよいのでチャレンジしていってほしいです。また、すでにできているという選手もより質の高い声が出せるように意識していってほしいですね。
声を出すことで少し下手な部分もカバーできますし、声出しができることで中学・高校になっても重宝されるような選手になれますよ。
YouTube 4:31~ 自分/チームの気持ち UP
まとめ
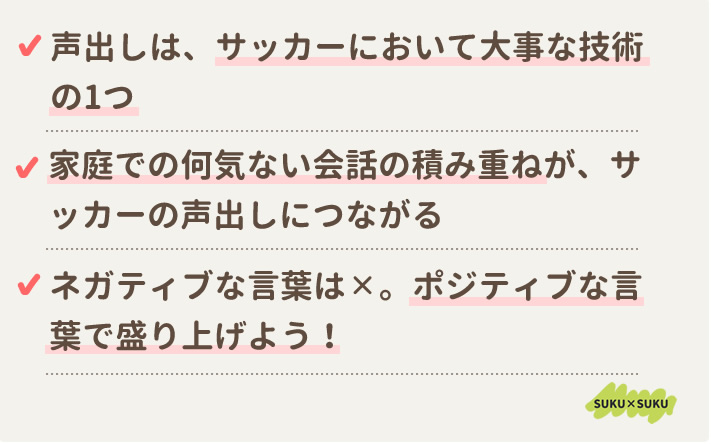
自分自身はもちろん、仲間やチームにもよい効果がうまれ、チームの勝利へも結びついてくる声出し。まさに、いいことづくめですね!
恥ずかしがりやさんで大きな声が出せない子や、何を言えばよいのか分からないといったお子さんも、まずは『家庭でできる声出しの練習3選』から始め、試合中に自然と『良い声』が出せるようにサポートしてあげたいですね。
今回ご協力いただいた教室
今回、ご協力いただいた『札幌市真栄サッカースポーツ少年団』塩崎 嵩仁コーチの詳細は以下のリンクからご覧ください。
コチラの記事も読まれています
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります