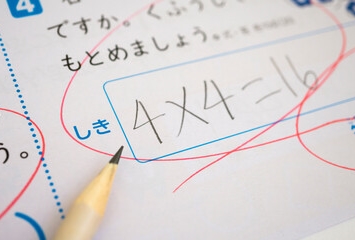宿題をやらない子どもにイライラ・・進んで取り組むようになる3つの対策とは?

小学校にあがると音読や計算カード、プリントなど毎日何かしらの宿題がありますよね。自ら進んでやってくれる子ならラクですが、ほとんどの家庭は「早く宿題しなさい!」「宿題もう終わったの?」と声をかけているのではないでしょうか?毎日同じことを言い続けるのもストレスがたまるし、できれば声をかける前にやってほしいですよね。そこで今回習い事スクスクは、心理学講師で3人のお子さんをもつ、やよいさんのブログに注目!子どもが進んで宿題をやるようになる3つの方法を実体験より教えていただきました。
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
- 宿題嫌いの子どもが変わった!やる気を引き出す3つの方法
- ①宿題に関して口を出さない
- ②宿題をやるタイミングは子どもにまかせる
- ③宿題のやり方も子どもにまかせる
- 子どもを変えようとするより自分が変わるほうがラク!
- まとめ
- 今回ご協力いただいた方
- こちらの記事も読まれています
宿題嫌いの子どもが変わった!やる気を引き出す3つの方法
①宿題に関して口を出さない

かつてのやよいさんは、宿題のことをあれこれ言い過ぎてお子さんとケンカになることもあったと仰います。そんなやよいさんが、あるときお子さんの気持ちを聞いてみたらこんなことを言われたそうです。

やよいさん
これからやろうとしていたのに、お母さんが「いつやるの?」と声をかけてくる。計算カードを書いていたら「先生から聞いている方法と違う」とお母さんに言われる。
こんな不満が子どもの口からたくさん出てきました。そりゃ宿題やりたくなくなるよね……と思い、心配しつつ口を出すことはやめたんです。
お子さんの本音を聞き、自身の声かけが宿題へのやる気を削いでいると気づいたやよいさん。子どものやる気をつぶさないようにするため、宿題に関してあれこれ口を出すことをやめたそうです。
②宿題をやるタイミングは子どもにまかせる
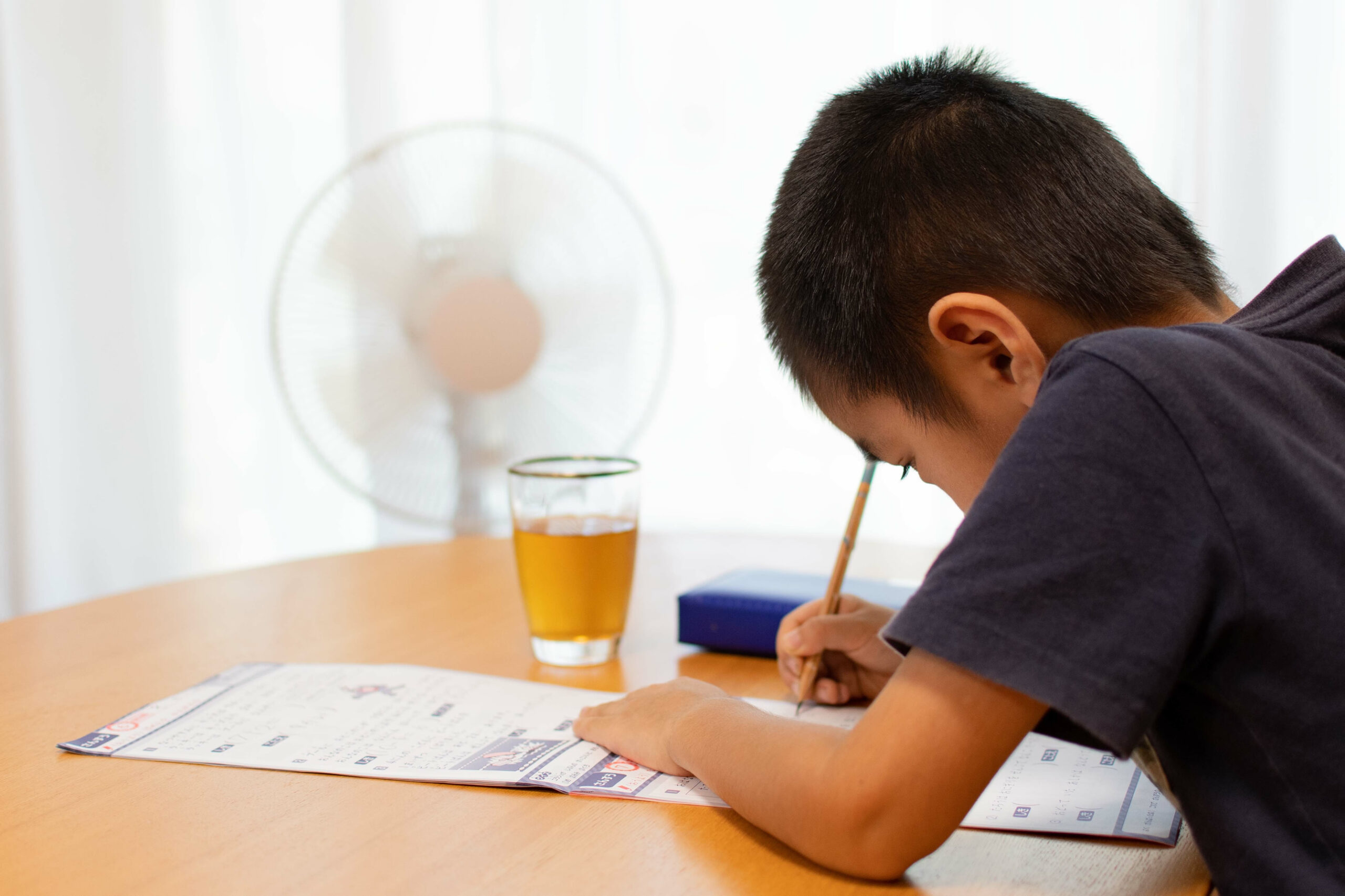
学校から帰ったら、宿題を済ませてから遊びに行ってほしいと思うのが親の本音ですよね。やよいさんもそう思っていたそうですが、ふと我が身を振り返り、宿題のタイミングを決めることもやめたと仰います。

やよいさん
たとえば自分が外出から帰ってきたとき、子どもたちにあれこれやってと言われても「まずは休憩させて!」と思っちゃいます。でもやらなければいけない時間までには、やろうと思っているんです。
そう考えると、学校から帰ってきた子どもに宿題や明日の準備をしろと言うのは申し訳ないことをしていたのかもな……と思いました。
宿題をやるタイミングは、完全にまかせることにしたやよいさん。すると、お子さんは前日に最低でも半分は終わらせるようにしたり、朝は自分で6時に起きて宿題したりと試行錯誤しながら取り組むようになったそうです。
たとえ宿題が終わらずにそのまま登校することになったとしても、それは仕方ないと仰るやよいさん。失敗を経験して改善していけるようになることを期待しそうです。
③宿題のやり方も子どもにまかせる

宿題をやるかやらないかだけではなく、やり方までも以前は気にしていたと仰るやよいさん。たとえば、プリントの書き方が先生の指示と違っていると「それでいいの?」と口を出していたのだそう。

やよいさん
子どもが自分で宿題をできるようになってほしいのであれば、宿題に対する親のこだわりを捨てることも大切だと思ったので、やり方をチェックするのもやめました。
多少書き方が違っていてもやっていればよし、むしろ私は見ないようにしました。計算カードもひとりでできるようにタイマーの使い方を教えたり音読は子どもが読み出したタイミングで聞くようにしたりと工夫しました。
やよいさんが宿題へのこだわりを捨ててお子さんにまかせるようにしたら、思いのほかスムーズに進むようになったそうです。初めは勇気がいるかもしれませんが、ときには子どもを信じてまかせてみるのもよいかもしれません。
子どもを変えようとするより自分が変わるほうがラク!

いままでは、決まった時間に正しい方法で宿題をやらせようとしていたとやよいさんは仰います。しかし、それではお互いにストレスがたまるだけだと気付き、自身の考え方や視点を変えた結果ずいぶんラクになったそうです。

やよいさん
口出しをやめることで子どもが困ったり泣いたりすることもあるけれど、結果を受け止め、自分のやり方を考えられるはず。そう信頼し、大事に囲っていた腕の中から離して見守ろうと決めました。
そうしてみたら意外と大丈夫で、子どもの成長を一層感じられるようになりましたよ。
子どもに限らず相手に何度注意しても変わらないと悩んでいたら、自分の考えを少し変えてみると予想外の展開が生まれるかもしれません。
口を出し続けることはエネルギーを消耗するので、なるべくラクをするためにも自分が変わることを考えてみるとよいかもしれませんね。
まとめ
- 宿題のことは口出ししない。思いきって子どもにまかせてみる
- 子どもを変えるより自分が変わることを考える
宿題を子どもにまかせることで心配ごとは増えるかもしれませんが、もしやらなくて学校で注意されてもその体験から感じることや学べることはあるはずです。
あれこれ言いたい気持ちをグッとこらえ、自主性を育む第一歩として宿題への関わり方を変えてみてはいかがでしょうか。毎日注意するより、案外効果があるかもしれませんよ。
今回ご協力いただいた方
今回取材にご協力いただいた、やよいさんの詳細は以下のリンクからご覧ください。
こちらの記事も読まれています
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります