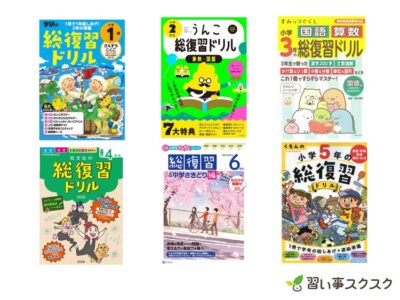小学生のうちに学習習慣をつけたいママパパ必見!効率のよい学習に必要な3つのポイントは?
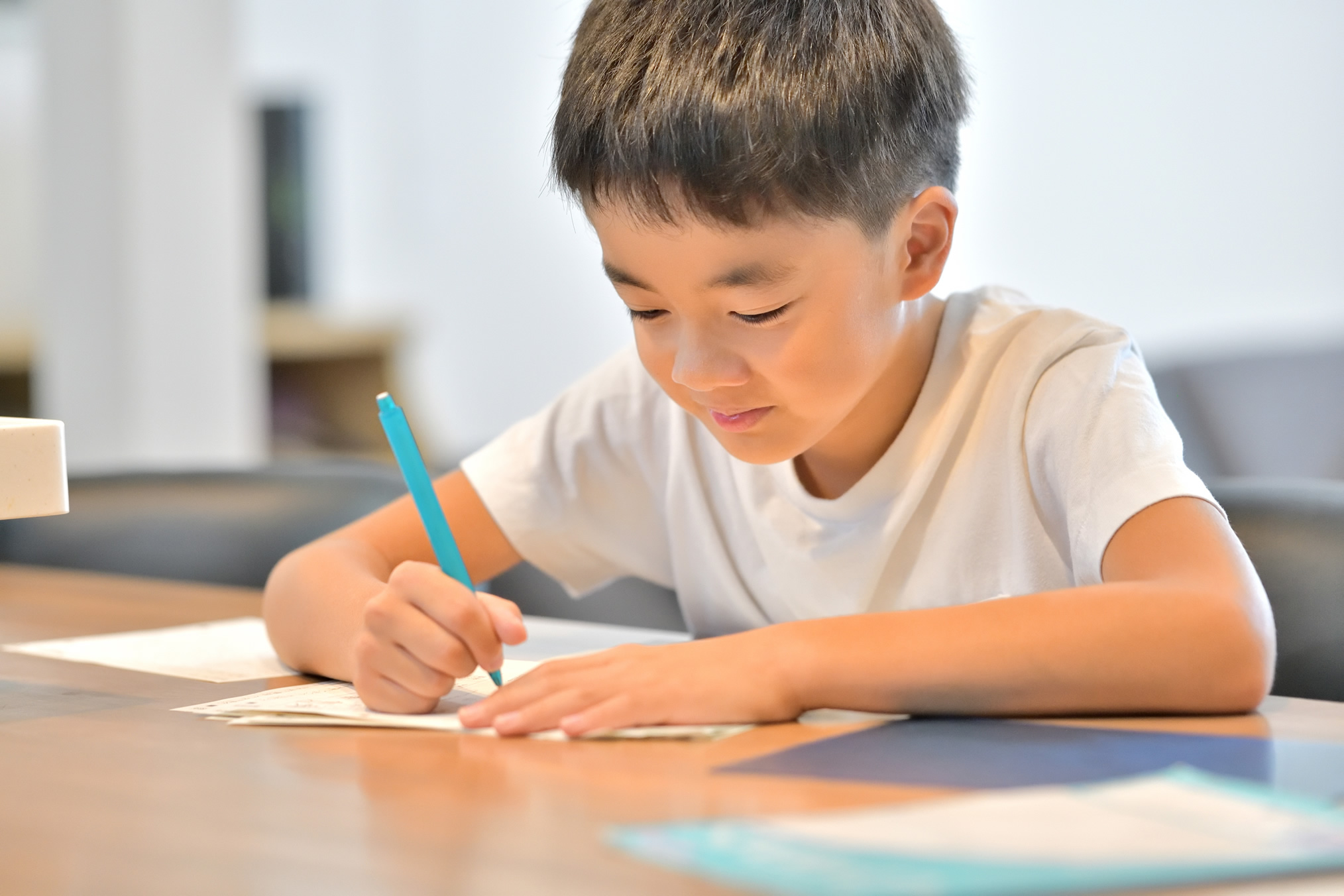
「小学生にはどのくらい勉強をさせたほうがいい?」「小学生の学習習慣ってどうやったらつけられる?」そんな疑問をお持ちの親御さんは多いのではないでしょうか。小学生での学習習慣は中学生になっても基盤になり続ける大切なもの。よい習慣は小学生のうちに身につけておけると安心ですよね。今回SUKU×SUKU(スクスク)は『オンライン家庭教師peace』のブログに注目。「小学生の勉強」について全3回にわたってご紹介していきます。第1回目は「効率よい学習に必要な3のポイント」です。
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
- 忙しい現代っ子に必要なのは「”効率のよい”学習習慣」
- 効率のよい学習に必要なこと ①勉強に最適な学習環境
- 効率のよい学習に必要なこと ②勉強しやすい最適な教材
- 効率のよい学習に必要なこと ③親のサポート
- まとめ
- 今回ご協力いただいた教室
- コチラの記事も読まれています
忙しい現代っ子に必要なのは「”効率のよい”学習習慣」
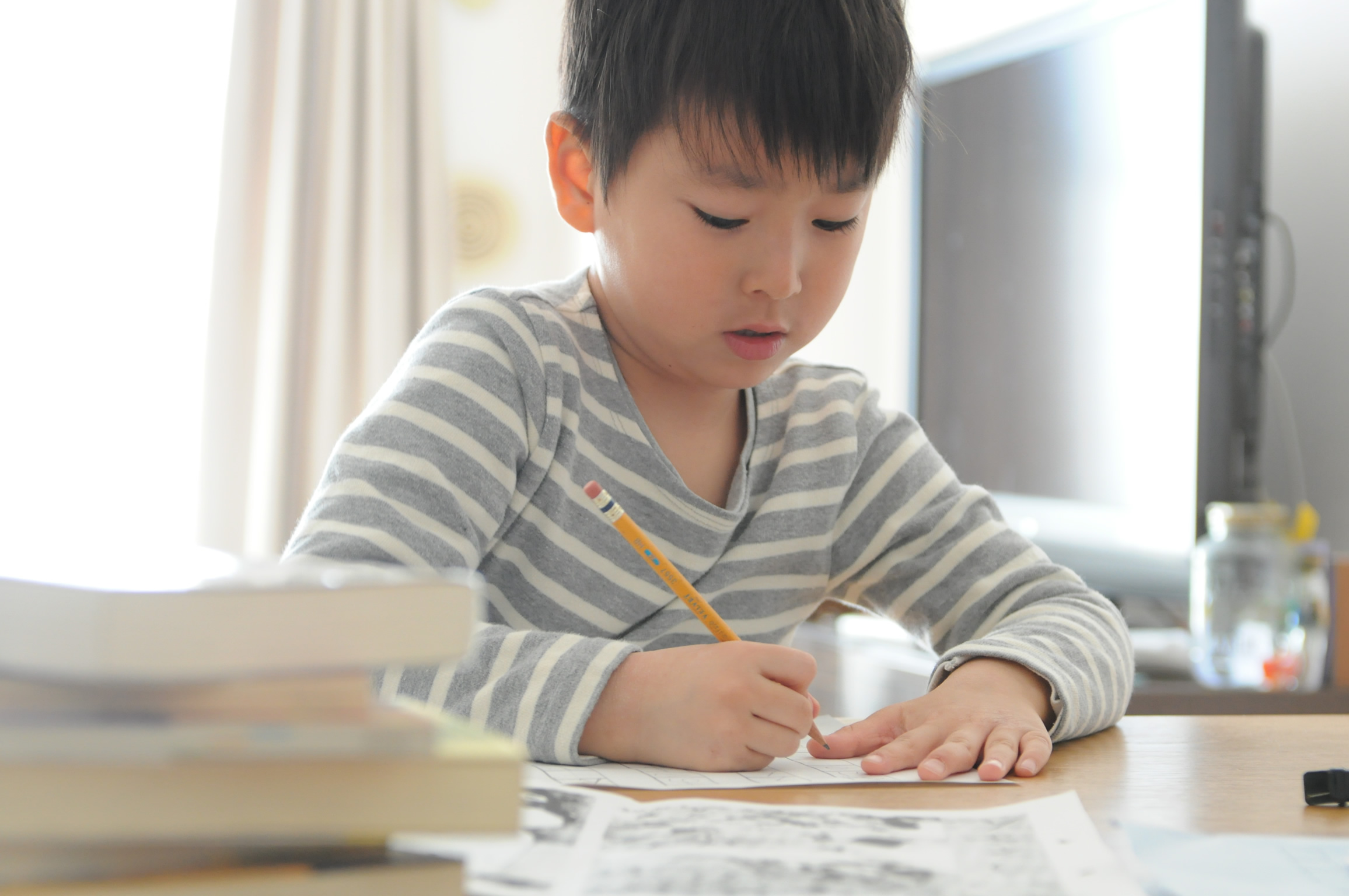
小学生のうちからさまざまな習い事をかけもちしているお子さんも多いいまの時代「毎日家で勉強時間を作るのは難しい」とお考えの親御さんは多いのではないでしょうか。
しかし小学生のうちから勉強の習慣を身につけられれば、今後のお子さんの武器となります。
それならば「できれば早いうちから勉強を習慣にしてあげたい」と考える親御さんもまた、多いのではないかと思います。
ということで、今回は、小学生が短時間で・集中して勉強するための「効率のよい学習に必要な3つのポイント」をご紹介します。
効率のよい学習に必要なこと ①勉強に最適な学習環境

「効率のよい学習に必要な3つのポイント」の1つめは、勉強に最適な学習環境を整えること。

永見先生
小学生の「最適な学習環境」とは、以下の5つを満たしているとよいでしょう。
1.机の上には必要なものしか出ていない
2.机は教科書やノートを広げる十分なスペースがある
3.必要なもの(辞書や資料集など)はすぐ手が届くところにある
4.「誘惑・娯楽」は視界に入らない
5.静か、しかし親の気配は感じられる
いかがでしょうか?お子さんの勉強の様子を思い返すと、部屋が散らかったまま勉強に取りかかってしまったり、いざ勉強を始めたのに、消しゴムがない!と探しまわっているうちに目についたもので遊び始めてしまったり……こんな光景が浮かぶ親御さんも多いのではないでしょうか。

永見先生
小学生はまだまだ自律の道半ばですから、スマホや漫画などの「誘惑」が目に入れば気になり、集中できなくて当然です。勉強以外のものは視界に入らないようにレイアウトを工夫しましょう。
「教材を十分に広げられるスペース」も、ストレスなく勉強をするためには大切なポイントです。
そして小学生は、親御さんの気配がするほうが勉強しやすいようです。家事の音は問題ないですが、テレビは消しておきましょう。音楽を流すのも小学生のうちはやめたほうがよいですよ。
■勉強に集中しやすい机のレイアウトとは
・テレビやおもちゃは、学習する机の背面がよい。
・目の前が壁よりも、壁を背にして部屋全体を見渡せる位置がよい。(壁が近いと圧迫感があり集中しづらいとされているため)
■十分なスペースとは
近頃の学習机のサイズで一般的なのは、幅100cm×奥行き60cmとされています。これは縦横どちらにも教材を2冊並べて広げられるサイズです。参考にしてみてください。
そして親御さんの気配が感じられることも、とても大切な要素だそう。
効率のよい学習に必要なこと ②勉強しやすい最適な教材
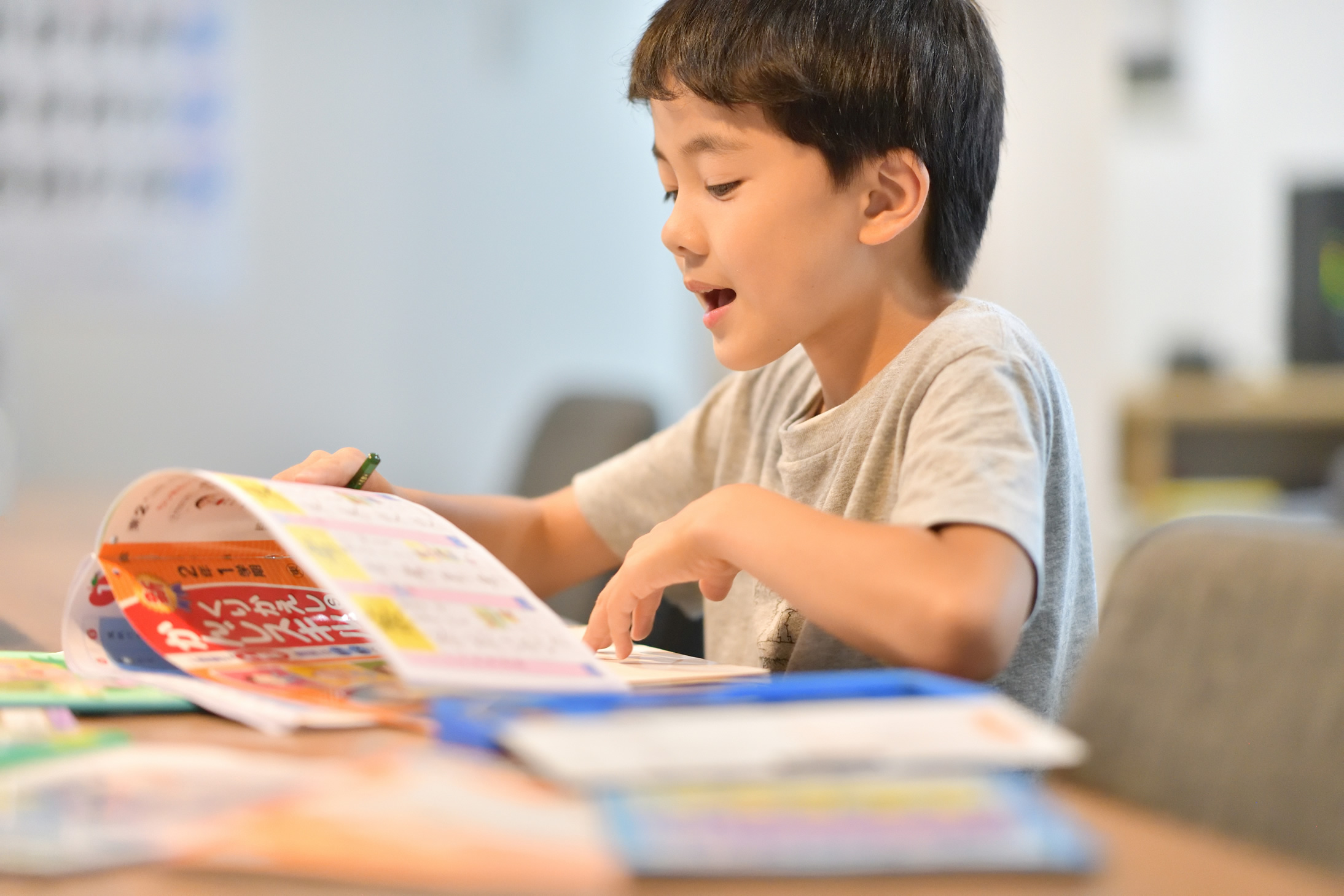
2つめは、勉強しやすい最適な教材を使うこと。
学校の宿題以外に、自習をするときの教材について永見先生はこのように仰っています。

永見先生
次の5つの条件を満たす教材が、効率的な学習には欠かせません。
1.子どもの理解度、習熟度に合ったレベル
2.子どもが達成感を感じられるもの(厚い1冊より、薄い数冊)
3.文字は小さすぎず、色合いやデザインは派手過ぎない
4.子どもの文字の大きさに合った十分な書き込みスペースがある
5.勉強の意欲を引き出す仕掛けがある(キャラクターなど)
こうしてみると教材選びって難しそう!と思われた親御さんもいらっしゃるかもしれません。5つの条件すべてを考慮した教材を見つけるのは難しい……という場合は、以下の2つをとくに重視して選ぶとよいのだそう。

永見先生
教材選びでとくに大切なのはこちらの2つです。
・お子さんの理解度、習熟度に合ったレベル
・お子さんが達成感を感じられるもの
これらによって、まず勉強の楽しさや達成サイクルを作り出すことが大切です。
学校の授業に合わせて勉強をする場合は「教科書準拠」「基礎・標準」という表記があるものがピッタリですよ。
「難しい」「分からない」「ゴールが見えない」これらは勉強への苦手意識を作ってしまう要因です。そのため「レベルが合っていること」と「達成感を感じられること」が大切なのですね。
また「十分な書き込みスペース」について永見先生はこのように仰っています。

永見先生
のびのびと字が書けることは大切です。たとえば筆算での間違いは、桁の不揃いが原因になることが多いです。
狭いスペースはミスのもと。勉強に必要な余白が不足していないかチェックしてみてください。
すでにお使いのテキストに十分な余白が少ない場合は、計算用の白紙プリントを用意してあげてもよいですね。
また、お子さんの意見も取り入れて一緒に選ぶと、主体的に取り組みやすくなるでしょう。
効率のよい学習に必要なこと ③親のサポート

3つめは、親のサポートです。
お子さんは親御さんの気配を感じられる、安心した環境でこそ集中力を発揮できるのだとか。永見先生はこんなお話をされています。

永見先生
「リビング学習」という言葉をお聞きになったことはありますか?文字どおり、子どもがリビングのテーブルで勉強をすることを指した言葉です。
リビング学習がよいと言われる本質は「子どもは親の近くだと安心できる、よって勉強に集中でき効率が上がる」という点にあります。
勉強をしている子どもの近くに親がいると、自然と勉強の様子を尋ねたり労ったりということが起きますよね。一緒に図鑑で調べたり、勉強したりということも起こりえます。
このように「親が近くで自分を見てくれている」という状態を、子どもたちは「親に応援してもらっている」と捉えるのです。親の応援を実感でき、安心して勉強に没頭できるというわけですね。
学年が下がるほどこの傾向は顕著で、一人で部屋にいると不安から集中力が下がるためリビングで勉強したい、というお子さんも多くいらっしゃるそうです。小学生のお子さんにとって親御さんの存在というのは、勉強をする上でもとても大切な役割を担っているのですね。
しかし、リビングで兄弟・姉妹が遊んでいて集中できないというご家庭も多いのではないでしょうか。そんなときは別部屋で勉強をさせてあげるほうが効果的なケースもあるそうです。
その際に気をつけたいことについて、永見先生はこのように仰っています。

永見先生
家族の会話があるときなどは、自室で勉強させることも効果的です。
ただ、お子さん自身が「ここだと集中できないから、自分の部屋で勉強する!」と思って行動することがもっとも大切です。
「兄弟・姉妹がいてもリビングで勉強したい」という場合は無理に別部屋を用意せず、多少気が散ってしまっていたとしてもお子さんの「落ち着く場所」を最優先する、という視点でまずは見守ってあげましょう。

また勉強をするお子さんへの声掛けについて、永見先生はこのように仰っています。

永見先生
お子さんには「困ったらいつでも教えてね」と話しておき、見守る・観察するぐらいのスタンスでよいと思います。
その上で、子どもから声掛けがあったら回答してあげるとよいですよ。
まとめ
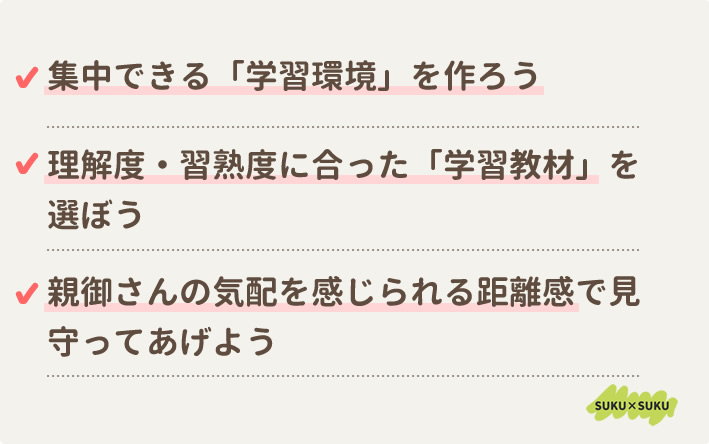
最適な学習環境、学習教材、親御さんのサポート、これら3つの要素を見直し、より効率的な勉強法を見つけられるとよいですね。
また効率よく短時間で勉強が済めば、余った時間で自由遊びもたっぷりとできます。子どもは勉強だけではなく、遊びを通してさまざまなことを学んでいきます。子どもたちには限られた時間の中でもたくさんのことを経験して成長していってほしいですね。
今回ご協力いただいた教室
今回、取材にご協力いただいた『オンライン家庭教師peace』の詳細は以下のリンクからご覧ください。
コチラの記事も読まれています
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります