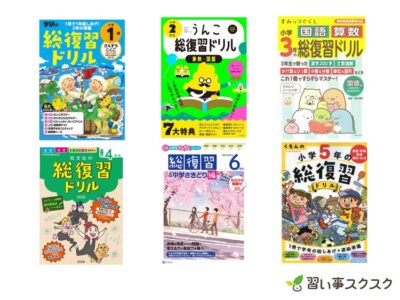スイミングあるある!?水泳中に足がつる原因と親子でできる対策

子どもにスイミングを習わせるとき、気になるのが泳いでいるときのケガや事故。とくに足がつると激痛で泳げないばかりか、肉離れを起こしたり、溺れる危険性もあります。練習がハードになる小中学生にもつりやすい子が多く、一度つると繰り返してしまうそう。今回SUKU×SUKU(スクスク)では『F.O.R.M.Sスイムクリニック』の尾崎優作先生のブログから、スイミング中に足がつる原因と対策を紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
スイミング中に足がつる原因と対策

泳いでいるといきなり足がつってしまうことってありますよね。「足がつる人は、繰り返しつる」と言われているようですが、ブログの中で尾崎先生の経験が次のように語られています。

尾崎先生
僕の場合、最初に足がつったとき腓腹筋が断裂、つまりふくらはぎが肉離れを起こしていました。
それから少し練習がハードになったり、量が増えて疲労が溜まってきたりすると、すぐにふくらはぎがつるようになりました。
ときどき肉離れも再発。
一回つると、痛くて一週間くらい泳げませんでした。
尾崎先生は足をつる瞬間が分かるようになり、つりそうになった場合は、すぐに泳ぐのを止めるのだそう。足がつる原因について尾崎先生はブログでこう語っています。

尾崎先生
運動で足をつるなどの筋肉の痙攣(けいれん)について、そのメカニズムははっきりと解明されていません。可能性としては次のようなことが考えられます。
①ミネラル、水分の不足

ミネラルのなかでも筋の収縮(ちぢむ)や弛緩(ゆるむ)に関係する「マグネシウム」や「カルシウム」が不足すると、足がつりやすくなるのだそうです。
ただし、筋肉がスムーズに動くために必要であることは分かっていますが、足がつることとどれほど関係があるかは明らかではないとのことです。水分についても同じだと尾崎先生はおっしゃいます。

尾崎先生
ミネラルや水分をいまより多めに摂ってみて、改善すれば、自分にとって必要な対策だったといえます。
ミネラルや水分の補給方法について、ブログで次のように語っています。

尾崎先生
ミネラルは天然塩、良質な野菜、魚介類の食事量をいまより多めにしてみるとよいでしょう。
水分は、練習前後に体重を量り、練習後に体重が大きく減らないくらいの量を飲みます。目安として、練習後にいつも体重が1kg減っているなら、必要な水分は1L程度です。
ただし、水分の適切な摂取量は個人差があるので、自分の体と相談しながら決めることが大事です。
ちなみに尾崎先生は、水分とミネラルの対策を徹底しても足がつっていたそうです。尾崎先生の痙攣の原因はミネラルと水分ではなかったようです。
しかし、直接の原因ではなかったとしても、スイミングやハードな運動をする人は、普段からミネラルや水分の補給を心がけておくことで、 痙攣を起こしにくい体作りができそうですね。
②疲労

尾崎先生によると、足をつることと疲労の関係は深く、2つのパターンがあるそうです。
・その日の練習がハードで、筋肉の疲労が限界に達して足をつるパターン
・何日もかけて蓄積した疲労が限界に達して足をつるパターン

尾崎先生
ケアを入念に行って疲労を取り除いてあげると足をつりにくいですよ。
ケアとしては、食べる、寝るは当然のこと、水泳以外の別のことをして心をリセットするとよいでしょう。
僕は必要であれば整体や鍼灸治療へも行きます。フォームローラーやゴルフボールを使ったストレッチ、呼吸法などもおすすめですよ。
心のリセットも大事なのですね。
たしかによくつる人、とくに子どもの場合は「また足がつって練習できなかった」と落ちこんでしまったり「またつるかもしれない」とプレッシャーに感じてしまうかもしれません。
これについて尾崎先生は次のようにブログで語っています。

尾崎先生
足をつらない人は本当にどれだけ泳いでもつらないですが、つる人はとことんつります。
仕方がないことなので、つらないように日頃からケアをしてあげましょう。
足をつらない人は本当にどれだけ泳いでもつらないですが、つる人はとことんつります。
尾崎先生曰く「足をつってしまうのは、仕方がないこと」なので、つらないように日頃からケアをしてあげましょう。
③過度な練習

たとえばダッシュをたくさんするなど、強度の高い練習をすると筋肉が酸欠状態になります。
そうすると筋肉をゆるめる神経とちぢめる神経のバランスが乱れ、疲労も加わって自分では制御できない筋肉の痙攣が起こるそうです。

尾崎先生
対策としては、練習中の定期的なストレッチやセルフマッサージが効果的です。そして、つりそうなときには無理をしないことが大切ですよ。
無理をしないためにも、自分が足をつってしまう練習のレベルを知っておくことが大切だと尾崎先生はおっしゃいます。過去の練習メニューをふりかえって、「危険なレベル」が分かっていれば、 自分で調整できるようになります。
しかし、子どもは泳ぐことが楽しかったり、上達することが嬉しくて自分の「危険なレベル」以上に練習してしまい、いつの間にか疲労をためこんでしまうケースもあるのではないでしょうか。
そのため「ケアを手伝ってあげることが大事」と尾崎先生はおっしゃいます。

尾崎先生
とくに小さいお子さんの場合は、コーチや親御さんが見守りながら、子どものやる気を尊重しつつ、ケアを手伝ってあげることが大事です。
スイミング教室では子どもの年齢や泳力に合うメニューを考えてくれますが、親御さんから見て練習後の疲れが取れにくいなど、気になることがあればすぐにコーチに相談しましょう。
足がつりやすい条件を知ることも大事

運動をすれば筋肉は疲労しますし、大会などの前にはいつもより練習がハードになってしまうものです。そのようなときは、この2つが大事だと尾崎先生はおっしゃいます。
・日々のケアと食事・睡眠
・自分の「危険なレベル」を知って無理をしないこと
そして、もう一つ大切なことがあるそうです。

尾崎先生
「危険なレベル」のほかに、自分がつりやすい条件も知っておきましょう。温度や水温、時間帯、季節、練習量なのか練習強度なのか、精神状態などです。
自分の足がつりやすい条件を把握することで、あらかじめ気をつけることができますね。

尾崎先生
僕の場合は、夜の練習で調子がよくて、泳ぐ量が多い日のラストのダッシュのクイックターン後がつりやすいタイミングです。
ここまで分かっているとかなり注意と対策ができます。
何度も足がつってしまう人は、自分がどんなとき、どんな条件でつってしまうか思い返してみましょう。小さなお子さんの場合は、親御さんがふり返りを手伝ってあげるとよいでしょう。練習ノートをつけるのもよいですね。
まとめ
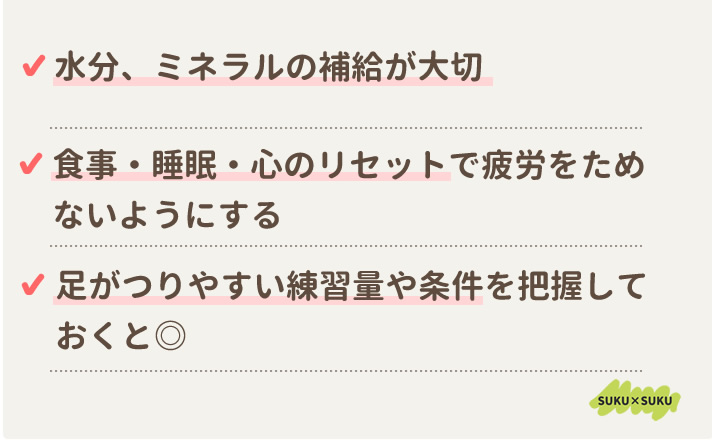
小中学生になって、練習がハードになると、足をつる子どもが増えてきます。子どもの場合は自分の疲労具合や限界がまだ分からず、無理をしてしまうこともあるでしょう。親子で一緒に足をつる原因と対策を知っておけば、無理をしないよう声かけをしたり、ケアを手伝ってあげられますね。
また、尾崎先生から学んだ対策は、筋肉の疲労による痙攣を起こしにくい体づくりができ予防効果も高いので、スイミングを始めたばかりのお子さんやママ・パパもぜひ参考にしてください。
今回ご協力いただいた教室
今回、取材にご協力いただいた『水泳個別指導F.O.R.M.Sスイムクリニック』 の詳細は以下のリンクからご覧ください。
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります