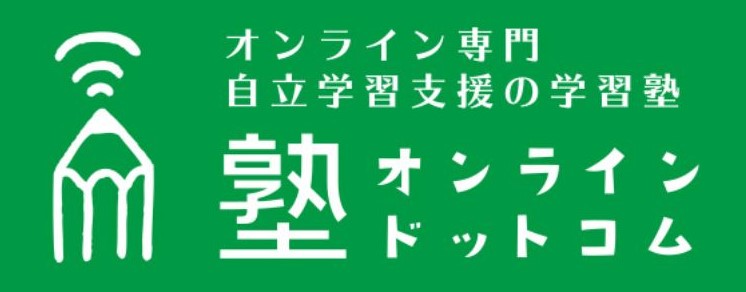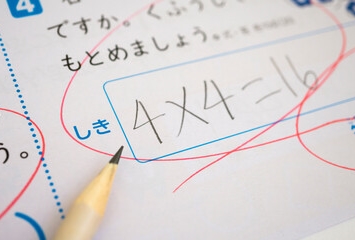【小6の保護者必見】先取り学習を焦ってない?数学の基盤になる「算数」の効率的な復習法

小学6年生になると、中学に行ってから苦労しないよう先取り学習に取り組む子が出てきます。なかでも「算数」は、中学生になると「数学」になり難しく感じられるせいか、先取り学習にも力が入る傾向にあるようです。しかし数学は積み重ねの教科と言われるように、算数を理解しないまま学習を進めてもつまずいてしまいます。そこで今回SUKU×SUKU(スクスク)は、オンラインで全国の小中学生に勉強を教える『塾オンラインドットコム』のブログに注目!中学生になる前にやっておきたい算数の復習方法について紹介します。
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
- 「数学」の先取り学習より「算数」の復習が必要な理由
- 算数の復習方法①同じ計算ドリルを繰り返し解く
- 算数の復習方法②重要な「3つの単元」を集中的に復習する
- 小学5年生で習う「割合」
- 小学6年生で習う「比と速さ」
- 小学6年生で習う「円の面積」
- 算数の復習方法③重要な公式はすべて暗記する
- まとめ
- 今回ご協力いただいた教室
- コチラの記事も読まれています
「数学」の先取り学習より「算数」の復習が必要な理由
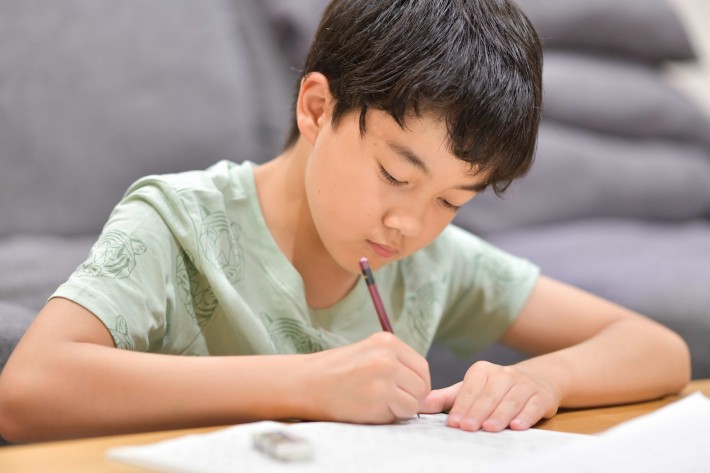
6年生になったら「数学」の先取り学習をする前に「算数」が理解できているか確認してみてほしいと仰るのは、塾オンラインドットコムの塾長・温品さん。
その理由について、ブログ内でこのように語ります。

塾長
算数は「答えを正しく求めること」が重要な教科です。一方で数学は、答えに至るまでの考え方が大切で「論理の正確性を求める」ことが必須とされています。
それぞれ重要なポイントは異なりますが、算数の内容を掘り下げたものが数学なので、算数が分からないまま数学を学習しても理解することが難しいのです。
焦って先取り学習をする前に、苦手な算数の単元がないかチェックして復習に力を入れるほうが数学力アップへの道は近いのだそうです。
とはいえ、算数の復習といっても6年間で学習した範囲は広すぎて何から始めたらよいのか分からないですよね。そこで塾長は、3つのポイントに絞って復習する方法を紹介しています。
算数の復習方法①同じ計算ドリルを繰り返し解く
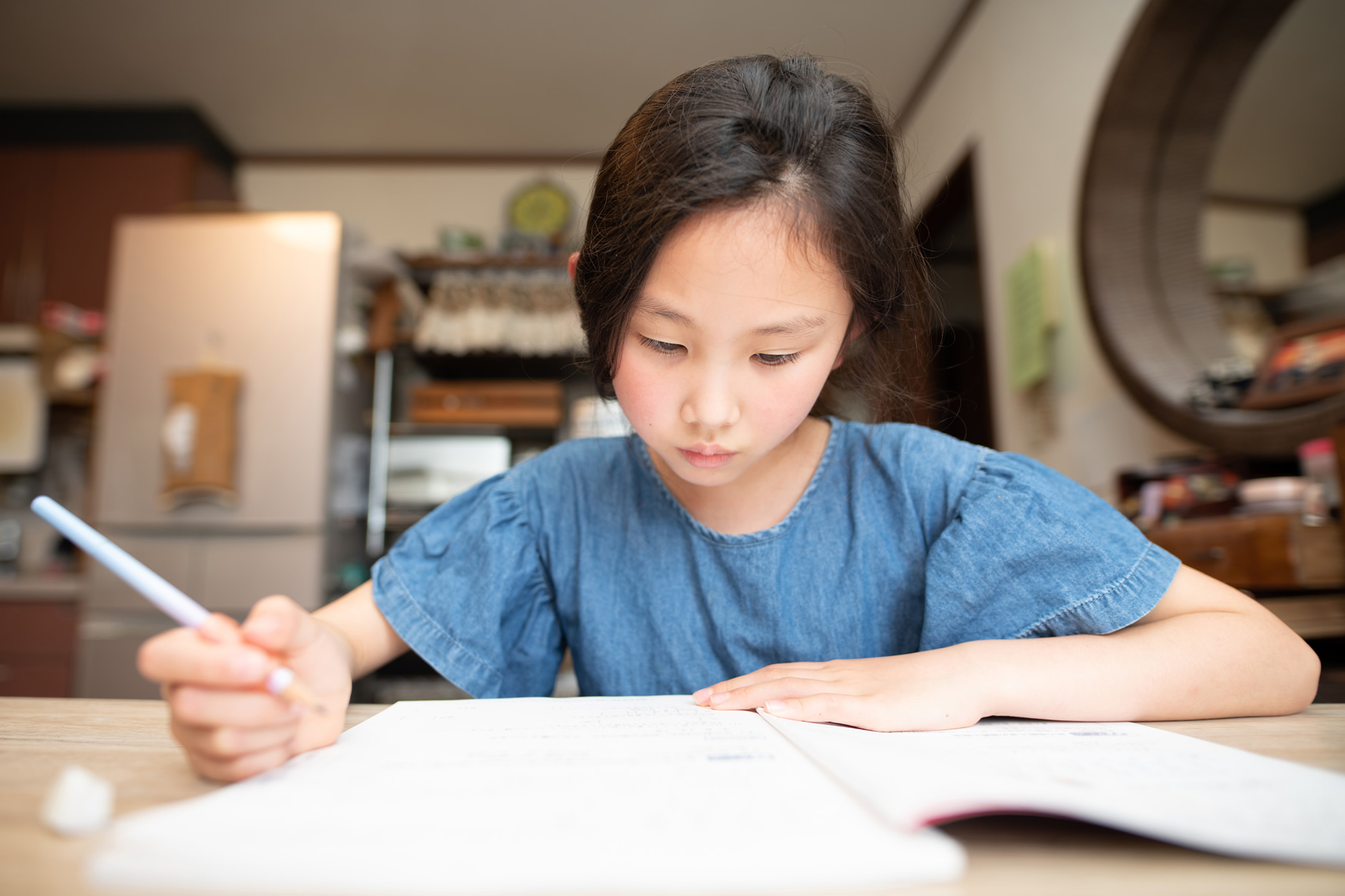
計算は、数学の基礎です。たとえ文章問題や図形問題の内容が理解できても、計算スキルによって正解か不正解かは変わります。まずは計算ドリルを使い、算数の基礎固めをしましょう。
1冊解き終えたら新しいドリルに取り掛かる子が多いかもしれませんが、塾長は同じドリルを繰り返し使うことをすすめています。

塾長
実力を身につけるためには、答えを暗記していても同じ計算ドリルを繰り返し行ってください。
繰り返し解くことで計算パターンを覚えられ、計算力も格段にアップするからです。間違えた問題だけ抜き出して、理解するまで何度も解くのもおすすめです。
算数の復習方法②重要な「3つの単元」を集中的に復習する

小学5年生で習う「割合」
ママパパにも覚えがあるかもしれませんが、割合の単元では「10gの食塩を150gの水に溶かして食塩水を作りました。この食塩水の濃度は何%でしょうか?」という問題が出てきます。
塾長曰く、割合は中学の数学でさらに複雑になるため、算数の時点で解を求める公式をマスターし、解き方を理解しておくことが必要だそうです。
小学6年生で習う「比と速さ」
「比と速さ」の単元では「速さ=道のり÷時間」の公式を基に、単純な計算問題から難しい文章問題まで幅広いパターンの問題が出てきます。
公式を覚えるのと同時に「単位」もこの単元のポイントです。「比と速さ」では「時速」「分速」「秒速」と3つの速さが存在します。さらに道のりを求めるときは「km」や「m」時間は「時間」「分」「秒」など、さまざまな単位が入り混ざって出題されるのです。
そのため、どの単位で回答を求められているかを理解して、時速を分速に変換するなどの計算力も必要とされます。
小学6年生で習う「円の面積」
「円の面積」の単元では、5年生で習得した円周率や円周の長さ、直径の長さを活用して、面積を導き出します。
そこからさらに発展して、おうぎ形やラグビーボールの形の面積を求める問題なども出てきます。「円の面積」では公式を使って求める方法を理解し、どこの長さが分かれば答えを導き出せるのか、思考する力が必要です。

塾長
「割合」「比と速さ」「円の面積」の3つの単元は、小学校の算数のなかでも難しい単元とされています。
理解していないと中学校で数学についていけなくなる可能性もありますので、小学生のうちにしっかり復習しておきましょう!
算数の復習方法③重要な公式はすべて暗記する

小学校の算数で習った公式は、中学校の数学でも使います。重要な公式はすぐに思い出せるよう、確実にマスターしておきましょう。

塾長
面積や体積、角度を求める公式はすべて暗記しましょう!たとえば
【面積】
・正方形 = 一辺 × 一辺
・長方形 = 縦 × 横
【体積】
・立方体 = 一辺 × 一辺 × 一辺
・直方体 = 縦 × 横 × 高さ
【角度】
・三角形の内角の和 = 180度
・四角形の内角の和 = 360度
など、これらは一部ですが公式を覚えておくと、図形の問題が苦手になりにくいと思います。
図形にまつわるものでなくても「公式」と名のつくものは、すべて暗記しておいて損はなさそうですね。
家庭学習でも、公式を集めたクイズを子どもと出し合ってみると楽しく覚えられるかもしれません。
まとめ
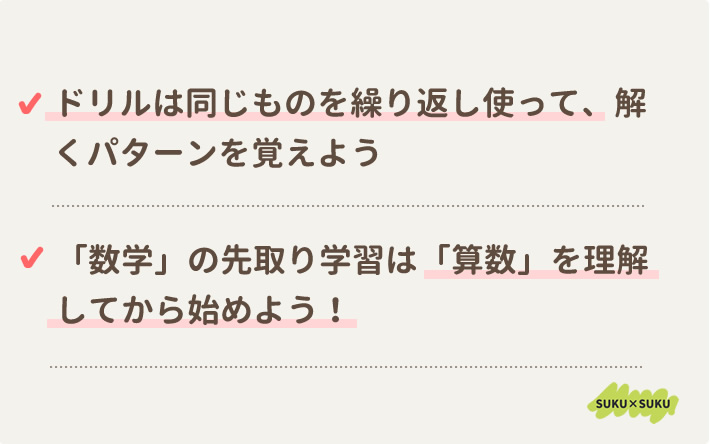
先取り学習ができていると子どもの気持ちにはゆとりが生まれますが、今までの学習が身についていないと後々苦労してしまうかもしれません。
算数に限らず先取り学習を進めようと思ったら、まずは小学校で習った単元がしっかり理解できているかぜひチェックしてみてくださいね。
今回ご協力いただいた教室
今回、取材にご協力いただいた『塾オンラインドットコム』の詳細は以下のリンクからご覧ください。
コチラの記事も読まれています
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります