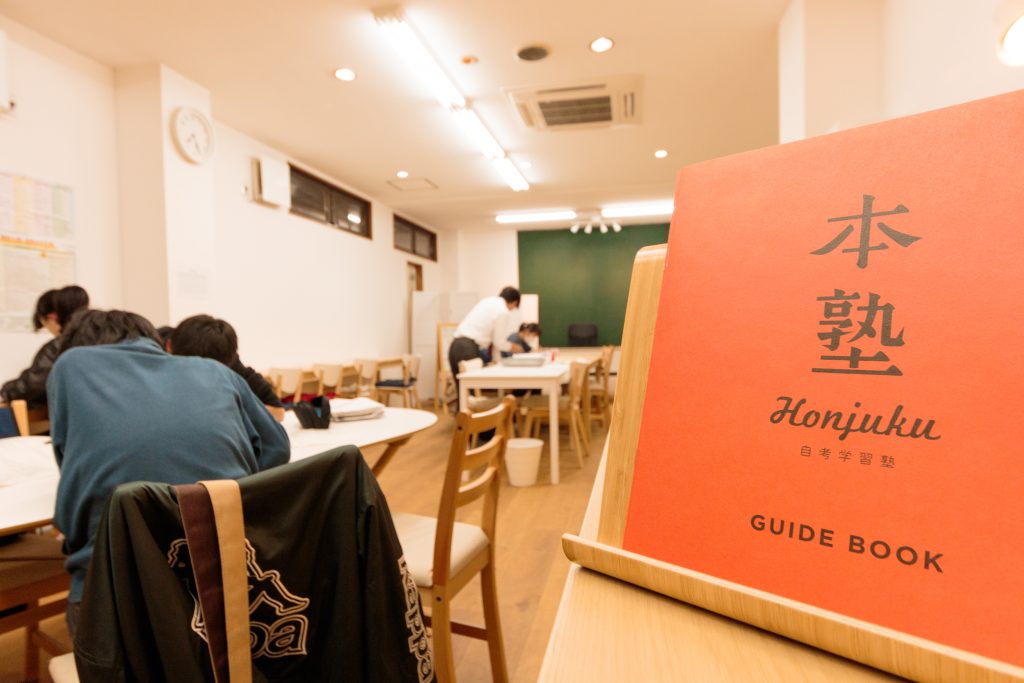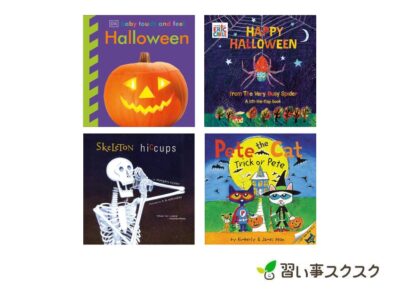塾に通わせるか悩んだときに見てほしい!塾講師が教える6つのチェックポイント
お子さんを塾に通わせたほうがよいのか、悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか。
こうしたお子さんのために今回SUKU×SUKU(スクスク)が紹介するのは、千葉県幕張本郷にある学習塾 本塾・塾長のブログです。ブログでは、塾に通ったほうがよいか迷っている方へのチェックポイントとして「勉強習慣が身についているか」「入試に準備すればいいことが分かっているか」など6つの項目が紹介されています。
※本ページはプロモーションが含まれます
目次
- ①学校の勉強を理解できているか?
- ②勉強習慣が身についているか?
- ③何を勉強すればよいか分かっているか?
- ④勉強のやり方が分かっているか?
- ⑤分からない所を質問できる人が身近にいるか?
- ⑥入試について、何を準備すればいいか分かっているか?
- まとめ
- 今回取材にご協力いただいた教室
- コチラの記事も読まれています
①学校の勉強を理解できているか?

水嶋塾長曰く、お子さんが塾に通うべきか判断するための1つめのチェックポイントは「学校の勉強を理解できているか」だといいます。
水嶋塾長のもとにやってくる子どもたちの多くは、塾に通い始めた頃「学校の授業内容がよく分からない」と話しているのだそう。

水嶋塾長
「いつから?」と聞くと、「ずっと前から」と答えたりするのです。
理由は、「小学校のレベルからつまずいていた」「学校の先生の説明が分からない」などさまざまですが、「集団授業のインプット形式が合わない」生徒も多くいます。
子どものタイプはそれぞれ違うので、大勢が同時に受ける学校の集団授業スタイルが合わない子どもも多いのかもしれません。
反対にそうしたお子さんが塾のような個人授業もしくは少人数制の授業スタイルの授業を受けることで、一気に理解度が高まるといったケースも多くあるのだそうです。
②勉強習慣が身についているか?

水嶋塾長は、勉強ができるようになるために必要なことは「勉強習慣」だとブログで話されています。
「自ら進んで机に向かう子どもになってほしい」という願いは、きっと親御さんの多くが持っていることと思います。

水嶋塾長
ただし、「自宅で勉強をさせたい」から塾に通わせるのはやめたほうがよいと思います。たいていの子どもは、塾に通うと塾の授業と宿題で勉強時間が増えます。
子どもにとっては、いままでよりも勉強しているので、家では余計に休憩したがります。そこで自宅でも勉強しなさいと追い詰めると、勉強が嫌いになり、塾にも通いたくなくなり、元に戻ります。
確かに学校の宿題にさらに塾での宿題も増えるとなると、子どもの心身への負担は大きいでしょうね。
では、どうすれば子どもの勉強習慣は身につくのでしょうか。

水嶋塾長
勉強ができるようになりたくない子どもは少ないので、勉強する体力が身につくまで待つことが大切です。
待つことは、親御さんにとってじれったく思えるかもしれませんが、お子さんが勉強習慣を着実に身につけられるためには、とても大切なステップ。
辛抱強く、見守ってあげたいですね!
③何を勉強すればよいか分かっているか?
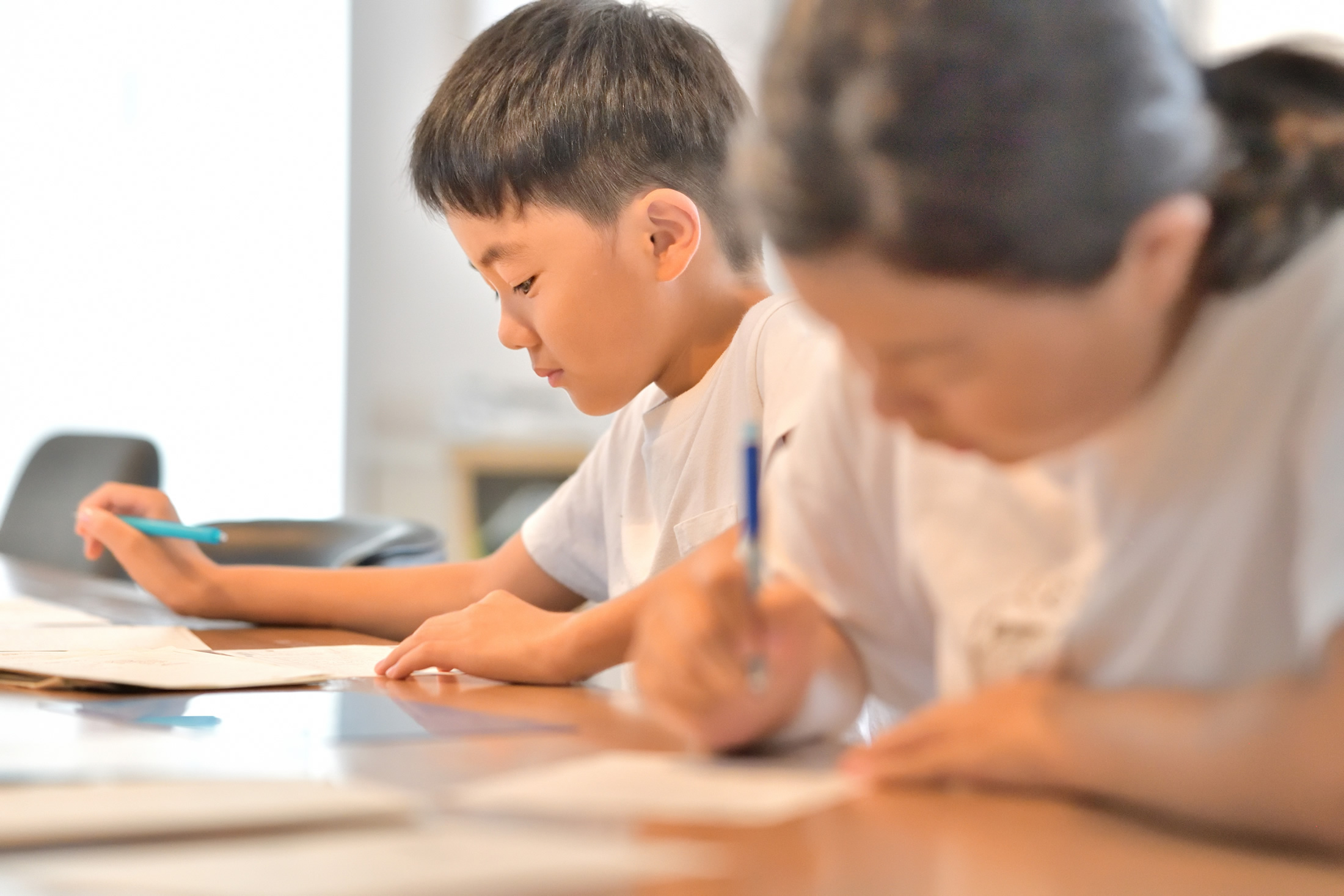
水嶋塾長が入塾してきた子どもにまず最初に教えることは、「何を勉強すればよいか」なのだそうです。
水嶋塾長曰く、勉強ができない子どもはこの「何を勉強すればよいか」について考えることができていないのだといいます。
反対に、これがきちんと理解できている子どもは当たり前のように授業の復習をしてテスト前になれば自ら進んでテスト勉強を行うのだそう。
では、どうすれば復習やテスト勉強に当たり前に取り組む子どもになるのでしょうか?

水嶋塾長
まずは、いつどんな勉強をすべきなのか?を理解することが大切です。その先に、自分に合った「どうやって勉強すればいいか?」という段階があるのです。
勉強ができるようになるには、やみくもに取り組ませるのではなく、まずは基本的な勉強の流れについてしっかりと把握させてあげることが大切なのですね。
④勉強のやり方が分かっているか?
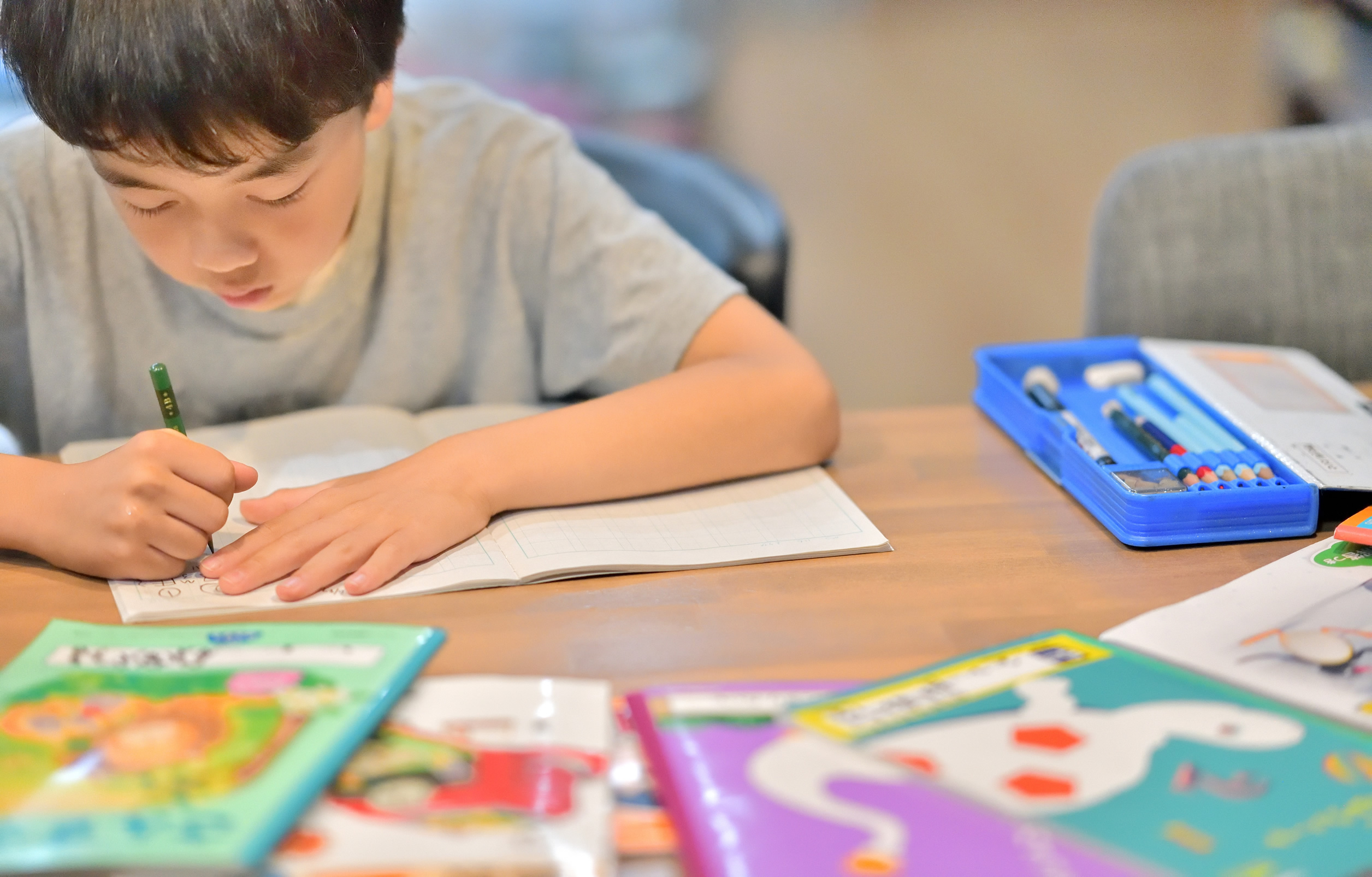
勉強ができない子どもには、さまざまなタイプがあるのだといいます。なかには「頑張ってやっているのに、まったく成果に結びつかない」というタイプの子どももいるでしょう。
水嶋塾長曰く、勉強ができない子どもには以下の4つのタイプがあるのだそう。
①宿題など、最低限のことだけやっていればいいと思っているタイプ
②ちょっとはやっているが、客観的に見るとほとんどやっていないと思われてしまうタイプ
③やることが優先で、何も成果が得られていないタイプ
④やり方が非効率で成果に繋がらず、やっていないと思われているタイプ

水嶋塾長
③④のタイプの子どもは、頑張って勉強に取り組んでいるのに直接的な成果に結びついていないので、結果だけを見て「勉強をやっていない」ととられてしまうことも多いでしょう。
お子さんがもしも③④のタイプであれば、勉強の効率が悪く、ひどく損をしてしまっていると考えられます。
自分なりに頑張って取り組んでいるのに、理解が進まずテストの結果にも結びつかない……
こうしたお子さんには、気持ちが折れてしまう前に、塾に通って勉強の効率を上げてあげることを検討してみてもよいかもしれませんね。
⑤分からない所を質問できる人が身近にいるか?

水嶋塾長は、子どもが「分からない」と感じているときは、勉強を一番吸収できるときなのだとブログで語られています。
けれどもここで大切なポイントが、「分からない所を質問できる人が身近にいるかどうか」なのだそう。

水嶋塾長
子どもが分からないと感じているときに聞く相手がいない場合は、大切なタイミングを失ってしまっています。タイミングを失ってしまった子どもは、「分からない」部分をそのままに忘れてしまいます。
それが積み重なることで、勉強ができない子どもが生まれてしまうのです。
現代では共働きの家庭も多く、子どもが自宅で学校の宿題に取り組んでいるときに親御さんが自宅にいないというシチュエーションは、多いのではないでしょうか。
こうしたことは仕方がないことではありますが、お子さんの勉強が伸びるせっかくの機会を逃してしまっているのだとしたら、とてももったいないことですよね。
⑥入試について、何を準備すればいいか分かっているか?
子どもによって目指す高校はさまざまですが、水嶋塾長はそれぞれの高校の入試に合わせて対策を練る必要があるとブログで仰っています。
たとえば千葉県県立入試の数学の問題では、「作図」「関数」「証明」が必ず出題されるそう。ですが、「作図」は中学1年生で習うのに、中学3年生で慌てて復習されるお子さんが多いようです。
他にも「関数」が苦手な子どもは、中学1年生の「比例・反比例」からつまずいているケースが多く、小学生の「割合」や「分数」からつまずいているといったケースも……。

水嶋塾長
入試で必要になる科目だけでなく、それぞれの入試に必要な能力、基礎力を身につけておかなければ、受験生になって慌てて勉強をし始めても、思うように成績が伸びていかないのです。
お子さんの将来を決めるための大事な入試ですから、やはり受験生の年になってから慌てだすのではなく、早い段階から、受かるために必要な能力・基礎力を身につける機会を与えてあげたいと思われる親御さんは多いかと思います。
入試の過去問題が手に入れば、おうちでもある程度の予測を立てて勉強に取る組むことはできるかもしれませんが、やはり本格的な入試対策となると、家庭内だけでは弱くなってしまうかもしれませんね。
まとめ
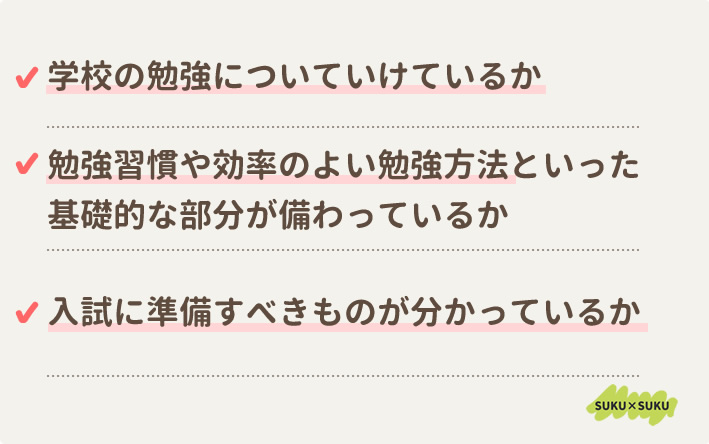
子どもを塾に通わせるべきかどうか、悩んでいる親御さんは多いことと思います。
お子さんのなかには、自ら進んで勉強に取り組む習慣がまだ身についていないというタイプや、自発的に勉強に取り組んでいるのにまったく成果に結びついていない……というタイプなど、さまざまなお子さんがおられることと思います。
なかには、勉強習慣や効率のよい勉強方法が身についており、塾に通わず親御さんのサポートのみで入試対策が可能なタイプのお子さんもおられるでしょう。
今回紹介した「お子さんに塾が必要かどうか判断するための6つのチェックポイント」を参考に、お子さんのタイプをきちんと把握したうえで、最適な道を見つけてあげてください。
今回取材にご協力いただいた教室
今回、取材にご協力いただいた「学習塾本塾」の詳細は以下のリンクからご覧ください。
コチラの記事も読まれています
当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります